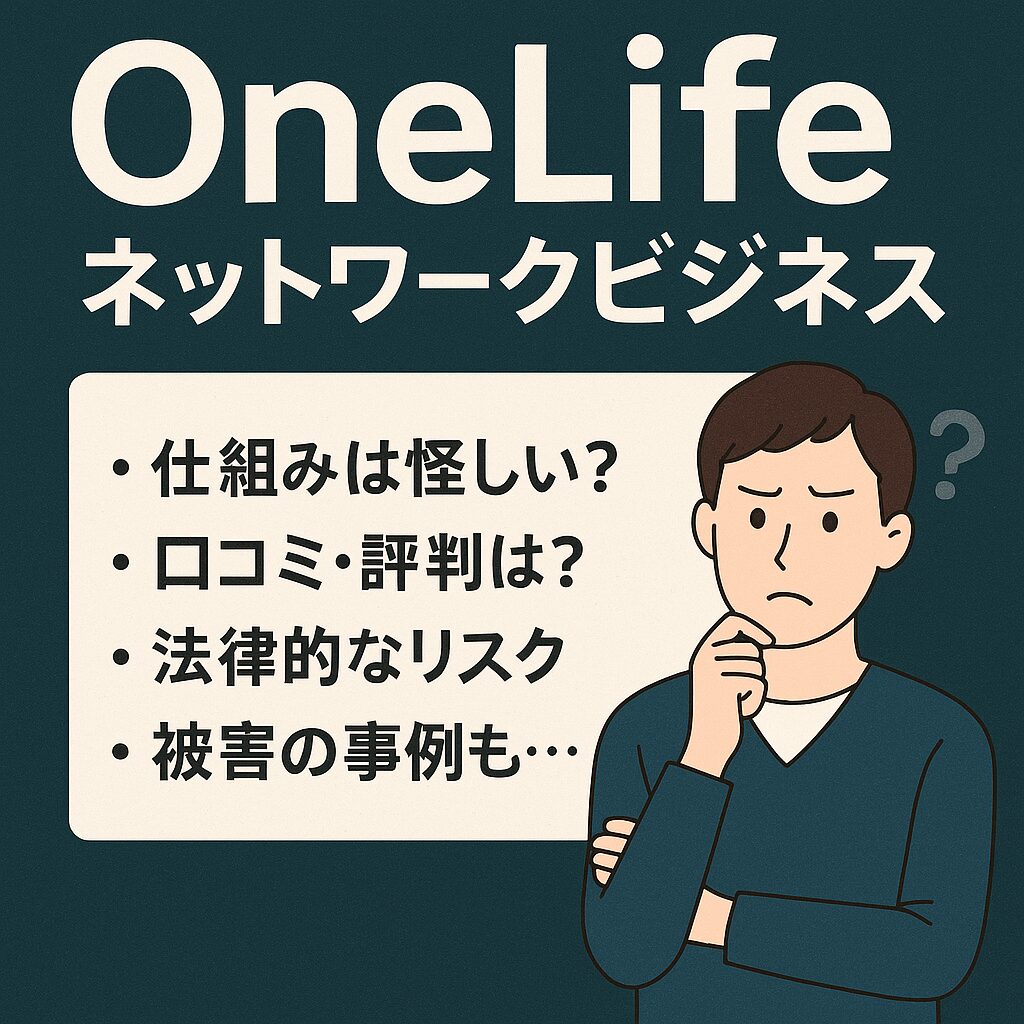最近ネットやSNSで見かけることが多くなった「OneLife」。自由なライフスタイル、高収入、世界を旅しながら働く…そんな夢のような言葉が並ぶこのビジネスですが、本当にそんなにうまくいくのでしょうか?
この記事では、OneLifeの仕組みや口コミ、法律的リスクから実際の体験談まで、知っておくべき全情報を徹底的に解説します。参加を検討している方も、すでに勧誘された方も、この記事を読むことで冷静な判断ができるようになります。
OneLifeとは何か?その仕組みとビジネスモデルを解説
OneLifeの概要と成り立ち
OneLife(ワンライフ)は、かつて世界中で注目を集めたネットワークビジネス(MLM:マルチレベルマーケティング)の一種で、仮想通貨「OneCoin(ワンコイン)」と連動したビジネスモデルで知られています。このプロジェクトは、2014年にルジャ・イグナトヴァという人物によってスタートしました。OneLifeは教育パッケージの販売を中心にしており、その購入者がOneCoinという仮想通貨を得られる仕組みでした。
しかし、最初から多くの専門家や規制当局がこのモデルに警鐘を鳴らしていました。というのも、OneLifeは実質的に「仮想通貨のマイニングができる」と謳いながら、その仮想通貨が実在せず、外部の仮想通貨取引所では取引できない閉ざされたシステムだったからです。そのため、一部では「ポンジスキーム(出資金を配当として回す詐欺)」と見なされ、世界各国で問題視されました。
日本でも一時期大きな広がりを見せましたが、金融庁からの注意喚起や、実際の会員の中で損失を被った人が続出したことにより、次第にその勢いは失われていきました。現在では、運営者の逮捕や訴訟に発展しており、信頼性が大きく揺らいでいます。
OneCoinとは?仮想通貨と連動した仕組み
OneCoinは、OneLifeのビジネスの中核をなす仮想通貨です。しかし、ビットコインやイーサリアムのように公開されたブロックチェーン上で運営されておらず、完全に内部管理された“中央集権型”の仕組みでした。つまり、発行量や価値は運営側が自由に操作できるという極めて不透明な構造です。
このOneCoinは、表向きは「教育パッケージ」を購入することで付与されるポイントのようなものであり、それ自体に法定通貨と交換できる実体はありませんでした。それにも関わらず、「将来的に上場する」「価値が何倍にもなる」といった誘い文句で、多くの人が勧誘されました。
また、外部の取引所では一切流通しておらず、売買はOneLife内の会員間のみ。つまり、外の市場からの需要や価格変動の影響を一切受けない“閉鎖経済”で、いわば運営会社の都合次第でどうにでもなる設計だったのです。
結果として、「仮想通貨」と名乗ってはいたものの、実際には通貨としての機能を果たしていなかった点が、多くの批判を浴びる原因となりました。
MLM(マルチ商法)との関係
OneLifeの最大の特徴は、典型的なマルチレベルマーケティング(MLM)モデルを採用していたことです。参加者は、教育パッケージを購入すると同時に、その販売者(アップライン)になり、さらに他人を紹介して参加させることで報酬を得ることができました。この構造は、上にいる人が下の人からの売上によって収益を得られる、いわゆる“ピラミッド型”です。
この手法自体は合法的に運営されているMLM企業でも使われていますが、OneLifeの場合は「製品が実質的な価値を持たない」「新規参加者がいないと報酬が得られない」といった点から、MLMの名を借りた投資詐欺とみなされるケースも多く、トラブルが続出しました。
実際、MLMは法律上グレーゾーンな領域も多く、しっかりとした運営でない場合には、詐欺的な手法と見なされる可能性も高いのです。
勧誘の流れと収益構造のカラクリ
OneLifeの勧誘は、主にセミナーや紹介制のイベントを通じて行われていました。内容は「この仮想通貨は将来、何十倍にもなる」「今なら早く始めた者勝ち」といった、希望に満ちた将来像を提示するものが多かったです。そして、その場で教育パッケージの購入を勧め、さらに紹介報酬が入るからと他人を誘うよう促されます。
収益の構造は、新しく加入した人の購入金額の数%が紹介者に還元されるという仕組みです。そのため、実質的には新規の参加者を増やし続けない限り、収益が続かない構造となっています。これは典型的な「ネズミ講」と類似しており、法律上でも問題とされる部分です。
初期に参加した人の中には、短期間で収益を上げたケースもありますが、参加者が増えなくなれば当然、下の層の人々は報酬を得ることができず、大きな損失を抱えることになります。
本当に稼げる?実際の会員の声と実態
「OneLifeで人生が変わった!」「自由なライフスタイルを手に入れた」といった声は、一部の成功者によって広められました。しかし、それらは主に上位層の紹介者であり、実際には大多数の会員が出資額を回収できないままビジネスから離脱しています。
口コミサイトやSNS、掲示板などには、「家族や友人を巻き込んでしまった」「借金までしてパッケージを買ったのに何も残らなかった」といった声が多く見られます。これらの投稿からわかるのは、勧誘文句と実態のギャップの大きさです。
また、特定のグループによる“洗脳的”なマインドセットの共有や、批判者を排除するような雰囲気もあったとされ、冷静な判断が難しくなる構造だったともいわれています。
OneLifeの評判と口コミを徹底調査
SNSや掲示板での評価は?
OneLifeに関する評判を調べると、SNSや掲示板で多くの意見が飛び交っていることがわかります。特にTwitter(現X)や5ちゃんねる、YouTubeのコメント欄などでは、参加者や第三者による賛否両論が目立ちます。ポジティブな意見では「先行者利益で収入を得た」「夢を見させてもらえた」といった声がある一方、「詐欺だと思った」「騙された人が身近にいる」といった否定的な評価も少なくありません。
多くの口コミに共通しているのは、実際に収益を得た人はごく一部であり、大多数は「お金を失った」「思ったように報酬が出なかった」といったネガティブな経験をしているという点です。特に後から参加した人ほど、利益を得るどころか損失を抱えている例が多いのが実態です。
SNSでは、「#OneLife被害」「#ワンコイン詐欺」などのハッシュタグも見られ、被害を訴える投稿も多く存在します。こうした発信は、参加を検討している人にとって貴重な情報源になります。口コミ情報を鵜呑みにするのは危険ですが、複数の情報を見比べることで、実態を冷静に判断することが大切です。
ポジティブな口コミに共通する点
ポジティブな口コミに目を向けると、いくつかの共通点が見えてきます。まず、OneLifeに対して良い評価をしている人たちは、主にビジネスの“初期段階”で参入した人たちであり、早期に報酬を得ている点が特徴です。また、「自己啓発」「成功者マインド」といった言葉を好んで使う傾向があり、ビジネスというよりも“自己成長”の一環として捉えている人が多いようです。
さらに、彼らはセミナーやコミュニティ内での連帯感を重視しており、「仲間と夢を共有できた」「前向きな気持ちになれた」といった感情的な満足感も評価の一部になっています。ただし、これらの口コミは実際の金銭的成功とは必ずしも一致せず、精神的な満足感を重視しているケースも多い点には注意が必要です。
また、ポジティブな投稿の中には、勧誘目的の投稿も少なくありません。報酬の仕組み上、自分が人を紹介すればするほど利益になるため、実態よりも良く見せようとするケースもあります。したがって、発信者の立場や目的も慎重に見極める必要があります。
批判的な口コミに見られるリスク要素
批判的な口コミで特に多く見られるのが、「最初に大金を支払ったが、何のリターンもなかった」「紹介すればするほど、周囲との関係が悪くなった」といった実体験に基づく後悔の声です。これは、ビジネスモデル自体が新規参加者からの資金に依存していたため、拡大が止まると一気に収益が出なくなる構造に起因しています。
また、「教育パッケージの中身が価値あるものとは思えなかった」「仮想通貨なのに売ることも使うこともできなかった」といった実用性のなさに対する批判も目立ちます。中には「騙されたと気づいた時にはすでに手遅れだった」という声も多く、精神的なダメージも大きいようです。
さらに、一部の勧誘者が強引な手法をとっていたことも問題視されています。「断ってもしつこく勧誘された」「嘘の実績を見せられた」といった報告は、ビジネスとしての信頼性を大きく損ねるものです。これらの口コミは、参加を考える上で冷静に受け止めるべき重要な警鐘と言えるでしょう。
実際に関わった人の体験談
実際にOneLifeに関わった人々の体験談には、さまざまなリアルなエピソードが含まれています。たとえば、ある男性は「成功者の話を聞いて感動し、貯金をはたいて参加したが、結局誰にも紹介できずに終わった」と語っています。また、女性の体験談では「最初は夢のある話にワクワクしたが、実際は仲間内での圧力やノルマに近い勧誘がつらくて辞めた」とのこと。
さらに、家族や友人に紹介したことで人間関係が壊れたという話も少なくありません。「信頼していた友人に断られて以来、気まずくなった」「親にも勧めてしまって後悔している」といった体験談は、ネットワークビジネスの特有のリスクを示しています。
こうした声からわかるのは、「収益化」だけでなく「精神的ストレス」や「人間関係の摩耗」といった目に見えないリスクも大きいということです。ビジネスを始める際には、金銭的な面だけでなく、こうした側面もよく考慮することが求められます。
被害報告はあるのか?その事例を紹介
OneLifeに関する被害報告は、日本国内外で数多く報告されています。日本では国民生活センターに対して「高額な商品を買わされた」「紹介した家族に責められている」といった苦情が寄せられており、行政側も注意喚起を出しています。海外では、創業者のルジャ・イグナトヴァが国際指名手配されており、アメリカではFBIが「重大な金融詐欺事件」として捜査を進めています。
具体的な事例としては、数百万円を投資したのに何の利益も得られなかったケースや、勧誘により家族や友人関係を失った例などがあります。被害者の中には、「生活が破綻した」「自己破産に追い込まれた」という深刻なものもあります。こうしたケースからも、ネットワークビジネスにおける信頼性や透明性の重要性がよくわかります。
さらに、こうした被害が起こる背景には「仮想通貨」や「投資」といった専門的な言葉を使った巧妙な勧誘手法があるため、十分な知識がない人ほど騙されやすくなっています。冷静に情報を見極め、慎重な判断を下すことが何よりも大切です。
法律的なリスクと注意点
ネットワークビジネスと法律の関係
ネットワークビジネス(MLM)は、正しく運営されれば違法ではありません。しかし、運営方法や勧誘手段によっては法律違反となるケースもあります。OneLifeのように「報酬が紹介によって得られる」モデルは、特定商取引法や景品表示法、さらには出資法など、複数の法律と密接に関係しており、ルールに反した運営を行えば違法になる可能性があります。
日本ではネットワークビジネスに対して厳しい目が向けられており、特に勧誘方法には細かい規制が設けられています。例えば、勧誘の際に「断りにくい雰囲気を作る」「事実と異なる説明をする」などの行為は、消費者保護の観点から問題視されます。また、金銭を直接投資して利益を得るタイプのビジネスモデルは、出資法違反となる可能性もあります。
OneLifeのように「仮想通貨を使った投資型ネットワークビジネス」の場合、金融商品取引法に該当する可能性があり、登録のない業者が運営すると違法になります。このようなケースでは、後に大きなトラブルに発展する可能性があるため、事前に法的な側面をしっかり確認することが重要です。
特定商取引法に抵触する可能性は?
特定商取引法は、消費者を保護するための法律で、訪問販売や通信販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)などに適用されます。OneLifeのようなネットワークビジネスも、当然この法律の対象となります。違反があった場合、業務停止命令や罰金が科されることもあり、軽視できない重要なルールです。
この法律では、勧誘の際には「事業目的の明示」「商品の価格や契約内容の説明」「契約書の交付」などが義務付けられています。つまり、口頭だけで契約を進めたり、商品や報酬に関して誤解を与えるような説明をすると、法令違反となります。また、クーリングオフ制度も適用されるため、契約後に一定期間であれば無条件で解約が可能です。
問題となるのは、これらの法律を知らないまま、または意図的に無視して勧誘を行うケースです。特に初心者の会員が上の人に言われた通りに勧誘してしまい、結果として違法行為に関与してしまうこともあります。ビジネスに参加する前に、法律の基本を知っておくことは非常に大切です。
金融庁や消費者庁からの警告はあるか?
OneLifeに関しては、過去に複数の国の金融当局や消費者保護機関から警告が発せられています。日本の金融庁や消費者庁は直接的な取り締まりを行っていないものの、各自治体や国民生活センターには多数の相談が寄せられています。海外では、ドイツ、イタリア、ブルガリア、アメリカなどの金融監督機関が「OneCoin(OneLife)は違法な金融商品である」と明言しており、公式に警告文書を出しています。
アメリカでは、創業者ルジャ・イグナトヴァに対して詐欺罪で起訴状が出され、FBIが国際指名手配をしています。また、イギリスやインドでも関係者が逮捕された事例があり、国際的に「危険なスキーム」として扱われています。こうした状況を見れば、日本での正式な警告が出ていなくても、十分に注意すべき事案であることがわかります。
これらの公的機関による警告は、「勧誘されたが本当に大丈夫なのか?」と疑問を感じている人にとって、非常に重要な判断材料となります。信頼性の低いビジネスに手を出す前に、公的情報のチェックは必須です。
勧誘活動で違法となるケース
ネットワークビジネスにおいて違法となる勧誘の代表的な例には、「報酬や成果を誇張して説明する」「事実と異なる将来の見通しを語る」「クーリングオフを妨害する」「会社名やビジネスの目的を隠して会う」などがあります。これらの行為はすべて特定商取引法に反し、罰則の対象となります。
OneLifeでは、セミナーなどの集団での勧誘が頻繁に行われており、その中には「短期間で大金が稼げる」「通貨価値が数倍になる」といった発言が確認されています。これらが事実でない、もしくは誤解を与えるものであれば、違法な勧誘行為となる可能性が高いのです。
また、友人や知人に対して「とりあえず話を聞くだけでいいから」と誘い出し、実際にはビジネスへの参加を強く迫るようなやり方もNGです。これは「事業目的の事前明示義務違反」にあたり、法的なトラブルにつながります。勧誘する側もされる側も、法律を意識しないままに活動することのリスクを理解しておく必要があります。
万が一トラブルになったときの相談先
ネットワークビジネスでトラブルに巻き込まれてしまった場合、早めに専門機関へ相談することが重要です。まず最初に相談すべきなのは、消費生活センター(全国共通番号:188)です。消費者トラブルに精通した相談員が対応してくれ、適切なアドバイスや対応策を提案してくれます。
また、法的に対処したい場合は、日本弁護士連合会の法律相談窓口や、地元の弁護士会を利用することもできます。金融商品に関するトラブルであれば、金融庁の相談窓口や**証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)**なども活用できます。
最近では、ネットでの被害情報を共有する掲示板やSNSもあり、同じような被害者が情報交換をしているケースも多く見られます。ただし、信頼性の高い機関に相談することで、トラブルの深刻化を防ぐことができます。早めに相談し、証拠(契約書、メール、SNSのやり取りなど)をしっかりと保管しておくことも、後の対応で非常に重要になります。
参加前に考えるべき3つのチェックポイント
自分に向いているビジネスかどうかの見極め
OneLifeのようなネットワークビジネスに参加する前に、まず考えるべきことは「自分にこのビジネスが本当に向いているのかどうか」です。ネットワークビジネスでは、他人を勧誘し、説明し、納得させる能力が必要不可欠です。つまり、人と関わることが好きで、かつ人間関係を広げる努力ができるタイプでないと、長く続けるのは難しいでしょう。
また、断られることが多いのもこのビジネスの特徴です。たとえば、友人や知人に勧誘を断られたり、怪しいと疑われたりすることは日常茶飯事です。こうした状況に耐えられる精神的なタフさも求められます。さらに、商品や仕組みをきちんと理解して説明できる論理力や勉強意欲も必要です。
このように、ネットワークビジネスは決して「誰でも簡単に成功できる」ビジネスではありません。自分の性格や得意分野と照らし合わせ、「本当に自分がやるべきビジネスなのか?」を冷静に見極めることが重要です。周囲に流されず、慎重な判断をしましょう。
リスクとリターンのバランスを把握する
ビジネスには必ず「リスク」と「リターン」があります。OneLifeのようなビジネスは、高額な初期費用(教育パッケージの購入)を必要としながら、その見返りとなるリターンが保証されていないという特徴があります。つまり、「ハイリスク・ローリターン」になってしまう可能性もあるのです。
例えば、OneLifeでは100万円以上のパッケージを購入したにも関わらず、収益がゼロだったという声も少なくありません。なぜなら、報酬は新しい会員を紹介しなければ得られない仕組みだからです。参加しただけでは何も得られず、積極的な勧誘活動が必要になります。
一方、リターンに関しては、勧誘に成功した場合に限り、紹介報酬やボーナスが得られる可能性はあります。ただし、それも一時的であり、長期的に安定した収入を得ることは難しいと言われています。リスクとリターンを冷静に分析し、「どこまでなら損しても後悔しないか」を自分の中で明確にしておくことが大切です。
周囲への影響と信用リスクの把握
ネットワークビジネスで最も大きなリスクの一つが、「人間関係の悪化」です。OneLifeでも多くの人が「友人を誘って関係が壊れた」「家族にまで不信感を持たれた」といった体験を語っています。勧誘が断られるたびに落ち込み、それでも紹介しなければならない状況に追い込まれると、精神的にも大きな負担になります。
さらに、紹介した相手が損をしてしまった場合、「あなたのせいで損をした」と非難されることもあります。そうなれば、信頼関係が崩れるだけでなく、最悪の場合には法的トラブルに発展する可能性もあります。自分だけでなく、周囲の人にとってもリスクとなるのがこのビジネスの難しいところです。
自分の評判や信用を守るためにも、「紹介する相手の人生にも影響を与える責任がある」という意識を持つことが重要です。人とのつながりを大切にしたい人ほど、この点を慎重に考えた方が良いでしょう。
継続的な収入は本当に得られるか?
OneLifeのようなネットワークビジネスでは、「継続的に収入を得る仕組みが整っているか?」をしっかり見極める必要があります。多くの場合、収入は“紹介した人数”に依存しており、継続的な収入を得るためには、新規会員を増やし続けなければなりません。つまり、市場が飽和したり、社会的に問題視され始めると収益はすぐに減少します。
実際、OneLifeでは初期の一部の人たちは報酬を得られましたが、時間が経つにつれて「稼げない」「紹介しても反応が悪い」といった声が増えてきました。これは、多くのネットワークビジネスが抱える“再現性の低さ”の問題です。安定収入を得るには、信頼できる商品と継続的な需要が不可欠ですが、OneLifeの場合、仮想通貨という不安定な要素が絡むため、より不確実性が高いといえます。
長く安定した収入を得たいと考えているのであれば、他の収入源や副業と比較しながら、収益性や持続性を冷静に分析することが必要です。
他の副業と比較したときの優位性
現代は副業が当たり前の時代となり、ブログ運営、せどり、動画編集、プログラミングなど、多種多様な選択肢があります。その中で、OneLifeのようなネットワークビジネスが他の副業と比べてどのような優位性を持っているのかを考えることは非常に重要です。
ネットワークビジネスのメリットとしては、「初期費用さえ出せばすぐに始められる」「在庫を持たなくていい」「時間の自由度が高い」といった点がよく挙げられます。しかし、これらの利点は裏を返せば、「初期費用の損失リスクが高い」「実体のない商品で信頼性が不安」「自己責任が大きい」というデメリットにもなりえます。
他の副業と比べて、スキルや努力の成果がダイレクトに反映されにくい点や、周囲の協力が必要であることなど、参入障壁は思った以上に高いと言えます。もし自己成長や収入の拡大を目的とするなら、スキルを身につけてできる副業の方が、将来的な安心感や自己効力感を得られる可能性が高いでしょう。
ChatGPT:
今後の展望と参加すべきかの判断基準
OneLifeの現在の動向と今後の見通し
OneLifeは一時期、世界中で急速に広がったネットワークビジネスの代表格として話題となりましたが、現在ではその勢いは大きく衰えています。理由は、運営元であるOneCoinの創設者ルジャ・イグナトヴァが2017年以降、行方をくらませたことや、複数の国で詐欺容疑による逮捕・起訴が相次いでいるからです。2023年にはルジャがFBIの最重要指名手配リストにも載り、グローバルな捜査対象となっています。
こうした状況から、OneLifeの将来に対して明るい見通しを持つことは困難です。公式のWebサイトも更新が滞っており、プロジェクトとしての活動実態は事実上停止していると見るのが妥当です。現在も活動を続けているグループがあるようですが、過去のような組織的拡大や利益の拡大は期待しづらくなっています。
このような背景を踏まえると、「今後復活するかもしれない」「再び価値が上がるかもしれない」といった希望的観測だけで判断するのは非常にリスクが高いといえるでしょう。冷静に現実を見つめ、客観的な情報を基に行動することが大切です。
運営会社の信頼性と継続性
ネットワークビジネスに参加する上で最も重要なポイントの一つが「運営会社の信頼性」です。OneLifeの場合、運営元であるOneCoin社(ブルガリアに拠点)は過去に多数の訴訟を抱えており、経営の透明性や持続性に大きな疑問符がついています。特に創業者ルジャの失踪以降、リーダー不在のまま曖昧な運営が続いている状況は、参加者にとって大きな不安材料です。
また、OneCoin自体が「公開されたブロックチェーンを持っていない」「価値が内部的にしか操作されていない」といった技術的な問題も指摘されています。このような仮想通貨は、信用が落ちれば一気に価値を失うリスクを抱えており、長期的に見ても安心して参加できるビジネスとは言い難いです。
一般的に信頼できるビジネスであれば、定期的な財務報告、公的な登録、実績の開示などが行われますが、OneLifeにはそのような透明性がほとんどありません。将来性を語るには、まず現在の信頼性と安定性が確保されていなければならないのです。
世界的な規制と仮想通貨業界の影響
世界中の規制当局は、仮想通貨とネットワークビジネスが結びついたスキームに対して非常に厳しい目を向けています。特に、明確な金融ライセンスがないまま「投資」や「通貨発行」を行うビジネスは、違法と見なされるケースが多く、摘発や処分の対象となりやすいです。
OneLifeもこの規制強化の波を大きく受けたビジネスのひとつです。仮想通貨業界全体の規制が進む中で、技術面でも法制度面でも透明性を求められる時代になってきました。そのため、旧来のように「将来価値が上がるから今のうちに買っておこう」といったあいまいな売り文句では通用しなくなってきています。
また、ブロックチェーン技術そのものは今後も発展していくと考えられていますが、それを悪用した詐欺的スキームは排除される方向に進んでいます。法整備が進んだ現在、OneLifeのような曖昧な仕組みのプロジェクトが再び大きく復活する可能性は非常に低いと言えるでしょう。
参加する前にすべき情報収集の方法
ビジネスに参加するかどうかを判断する前に、正しい情報収集を行うことが非常に重要です。特にネットワークビジネスや仮想通貨のように専門知識が求められる分野では、公式情報だけでなく、第三者のレビューや専門家の意見を参考にすることが効果的です。
具体的には、以下のような方法で情報を集めることが推奨されます:
-
消費者庁や金融庁の公式サイトで警告情報を確認
-
SNSや掲示板での口コミを幅広くチェック(ただしステマに注意)
-
YouTubeなどの動画解説で仕組みを視覚的に理解
-
弁護士やFP(ファイナンシャルプランナー)など専門家に相談
-
実際の参加者の体験談を複数比較して見る
こうした情報を集めることで、感情的な判断ではなく、論理的・客観的に判断が下せるようになります。特に「うまい話には裏がある」という視点を忘れずに、冷静な判断材料を揃えていくことが、後悔しない選択につながります。
参加する価値はある?冷静な判断のすすめ
結論から言えば、現在のOneLifeに参加することの「価値」は極めて低いといえます。過去の経緯や運営状況、そして数多くの被害報告を見る限り、参加するメリットよりもリスクの方が圧倒的に大きいです。すでに事実上の“終わったプロジェクト”であり、再起の兆しもほとんど見られません。
それでも勧誘を受けたり、興味を持ってしまった場合には、まずは冷静になって以下のポイントを考えてみてください:
-
これは自分に本当に必要なビジネスか?
-
投資額を失っても精神的に耐えられるか?
-
勧誘した相手が損をしても自分は責任を取れるか?
-
他にもっとリスクの少ない副業はないか?
これらの問いにYESと答えられないなら、参加は見送るべきです。時代は確実に「自分のスキルで稼ぐ」方向へとシフトしています。今こそ、地に足のついた収入源を模索する時なのではないでしょうか。
まとめ:OneLifeに手を出す前に、冷静な目で事実を見よう
OneLifeは、一時期多くの人が夢を託したネットワークビジネスでした。しかし、その実態は仮想通貨OneCoinという透明性のない仕組みを土台にした、非常にリスクの高いビジネスモデルでした。SNSや掲示板には、被害の声や後悔の投稿が多く見られ、実際にトラブルや訴訟に発展した事例も世界中に存在します。
法律的にもグレーまたはアウトな側面が多く、特定商取引法や金融商品取引法に抵触するリスクをはらんでおり、無知のまま勧誘活動を行えば、自分自身が加害者になる可能性すらあります。また、運営会社の信頼性も低く、世界各国で規制や摘発の対象になっている現状を見れば、「今から始める価値がある」とは到底言えないのが実情です。
今後、副業や自由な働き方を目指すのであれば、より透明性が高く、自分自身のスキルや努力が反映されるような分野を選ぶ方が、長期的には圧倒的に安心で現実的です。もしOneLifeへの参加を迷っている方がいれば、一歩立ち止まり、このブログを参考に、冷静な判断をしていただけたら幸いです。